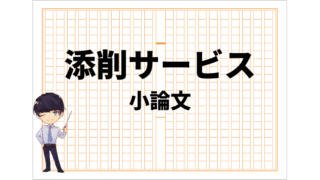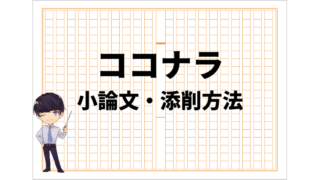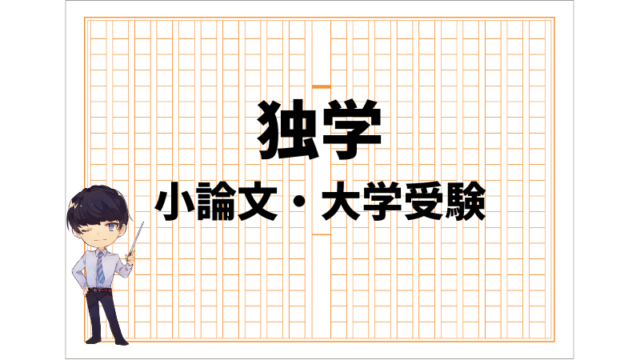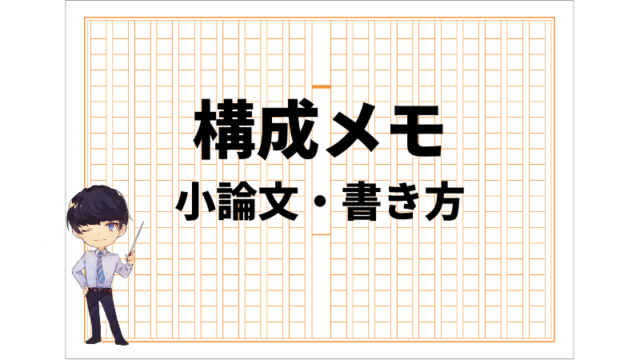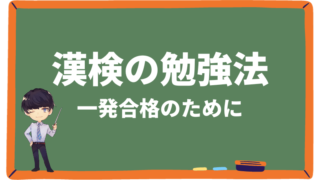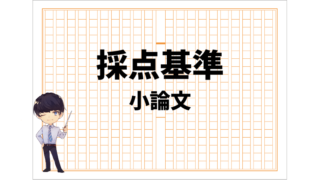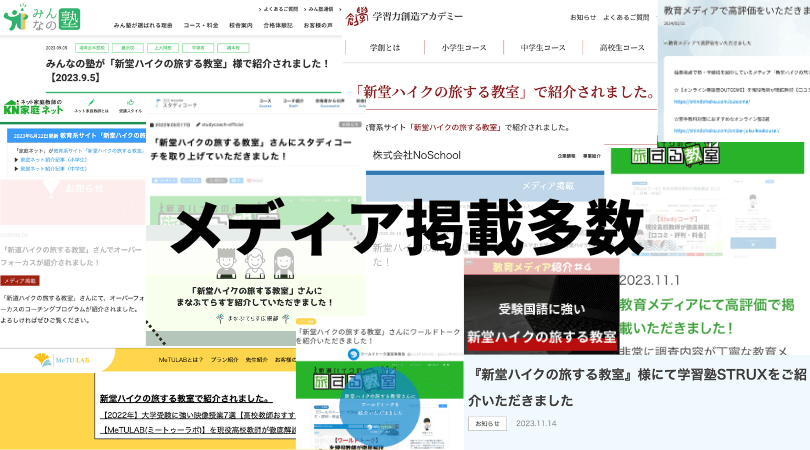こんにちは!
高校教師の新堂ハイクです!
小論文の書き方が分かりません…。
心配しなくても大丈夫です。小論文が書けないのは当たり前なんです。
なぜなら、国語の授業でも「小論文の書き方」は教えないからです。
でも授業で教えてくれないくせに、入試には割とよく出てくる小論文。
先生に書き方を教わりに行っても、
とりあえず、過去問かなんか見て書いてきて!
って言われて、
いや、何をどう書くかすら分からないから、全然書けないんですけど…。
ってなる人も多いと思います。
現役の国語教師である僕にお任せあれ!
このページであなたを、ある程度の小論文が書けるレベルに押し上げます。
これまで1000人以上の添削と、難関大合格の実績を持つ僕が、レベル0の小論文初心者をレベル50の中級者まで引き上げるために小論文対策の全てをまとめました。
・小論文とは?
・小論文の基本的なルール
・小論文の書き方
・写せるテンプレ例文
・小論文の出題形式、頻出テーマ
・小論文の勉強法、参考書
10分程度で読めますので、ぜひ最後までご覧ください!
.jpg)
著者 新堂ハイク 30歳
・現役高校教師 勤続9年(特進クラス担任)
・難関大受験、小論文指導実績500人以上
・教育メディア運営7年(月間10万PV)
・執筆300記事以上、掲載企業50社以上
実際の教育現場にいる現役教師にしか分からない、リアルな情報をお届けします!
小論文とは何か?
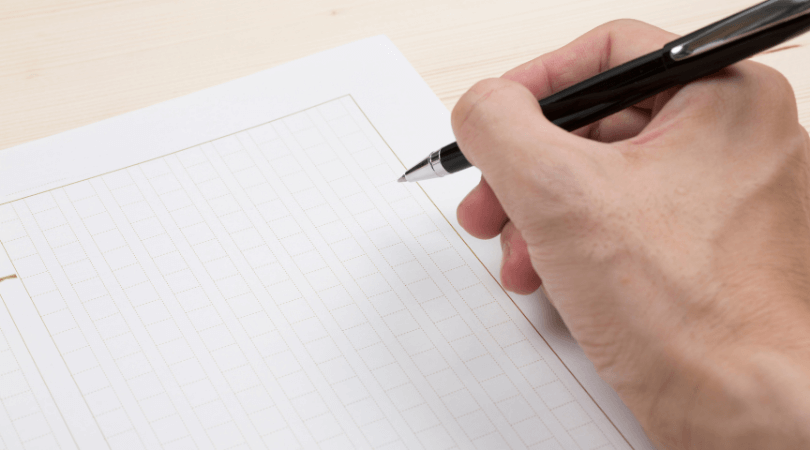
はじめに、「小論文とは何か」から解説します。
「もうそんなことはわかってるよ!」という方は読み飛ばしてもらって大丈夫です。
小論文とはこのような文章のことを言います。
自分の意見を論理的に説明し、読み手を説得する文章
よく「あなたの小論文は作文です」と言われる人がいますが、作文と小論文の違いを理解してこそ、小論文の勉強の第一歩です。
小論文と作文の違い
作文や感想文は個人の経験や心境をもとに、豊かな表現を使って読み手に「伝える」ための文章です。
小論文は自分の意見を論理的に説明し、読み手を納得させ「説得する」ための文章です。
作文
僕は最近寝る直前までスマホを見ている。すると朝起きるのが遅くなり、遅刻が増えてしまった。スマホが原因だと思うから、寝る前にスマホを見るのは良くない。
小論文
スマホの光に含まれるブルーライトの刺激を受けると脳は「メラトニン」という睡眠を司るホルモンの分泌を抑制するので、睡眠の質が下がる。だから寝る前にスマホを見るのは良くない。
どちらがより「説得力のある文章」かはすぐに分かりますよね。
作文は自分の「感覚」や「感想」で書かれているのに対して、小論文は「事実」や「意見」で書かれています。
誰かを説得するときは、相手が納得するような事実や意見を述べるのが基本です。
小論文が作文だと言われてしまう人は、「自分の感想」だけを書いている可能性が高いです。
小論文には意見が必要
小論文には読み手を納得させ、説得するための「意見」が必要です。
この「意見」と「感想」を間違えてしまうと、作文だと言われてしまいます。
意見と感想はどちらも「自分の考え」という点では同じです。
ただ、感想は「個人の主観をただ述べる」だけであり、そこに目的は存在しません。
意見には「個人の主張を述べて、提案をする」という目的があります。
感想
授業中に寝るのは良くないと思った。
意見
自分の学力を下げる原因になるので、授業中に寝るのはやめよう。
意見は「どうするべきか」という提案を相手に投げかけるものです。
小論文とはこのように自分の意見を使い、相手を説得する文章なのです。
小論文の基本的なルール

入試の小論文はたいてい原稿用紙に書いていくことになるのですが、原稿用紙の使い方にはルールがあります。
また「小論文で使ってはいけない表現」もあるので、書く前に覚えておきましょう。
これらのルールは基本中の基本で、間違っていると減点対象になります。
入試では1点2点の差が命取りになるので、文章のルールは必ず覚えましょう。
原稿用紙の正しい使い方
・書き出しは一字下げる
・段落を変える場合も改行して一字下げる
・「っ」「ゃ」「ゅ」「ょ」は一文字として扱う
・句読点「、」「。」
かぎかっこ「」は一文字として扱う
→ただし、行の一番上にくる場合は、前の行の一番下に入れる
・「!」「?」「…」などの記号的表現は使わない
・縦書きの場合、数字は必ず漢数字を使う
横書きの場合は、漢数字・算用数字どちらでも可
・アルファベット
大文字は一マスに一つ
小文字は一マスに二つ
原稿用紙の使い方なんて小学生以来だから、全然覚えてません…。
コツとしては、一回書いてから文章を見直すときに、上記のポイントをよく確認するクセをつければ自然にマスターできます。
原稿用紙の使い方は入試ではかなり厳しく見られるので、大幅減点にならないように気を付けてましょう。
常体で文体を統一する
「常体」とは文末が 「~だ。~である。」調の語尾になっている文章のことです。
小論文は「~です。~ます。」調の語尾ではなく、「~だ。~である。」で全て統一します。
小論文で使うべき語尾
・~だ。
・~である。
・~だろう。
・~ない。
・~と考える。
・~したい。
・~べきだ。
ちなみに「~だ、~である」と「~です、~ます」が混ざった文章になっていると、大幅減点です。
一人称は男女とも「私」
一人称は男女とも「私」で統一します。
「僕」や「自分」と表記してはいけません。
また、身内の呼称にも気をつけましょう。
| 悪い例 | 正しい例 |
| お父さん、お母さん | 父、母 |
| お兄ちゃん、お姉ちゃん | 兄、姉 |
| おじいちゃん、おばあちゃん | 祖母、祖父 |
| おじさん、おばさん | 叔父、叔母 (伯父、伯母) |
| 友達 | 友人 |
一文は短くする
一文は簡潔に短く書くのがコツです。
4行以上(80文字以上)の文があると読みにくく、違和感のある文になってしまう可能性があるので、一文は長くても3行(60文字)以内に収めるように意識しましょう。
文学的な表現は使わない
読み手の感性に訴えかけるような、詩的な表現はしてはいけません。
・自分の想い
→自分の感情・心境・心情
・小説のような表現技法
→比喩表現や擬人法・擬音語・擬態語・擬声語
これらの表現は論理的な文章では使わないので、避けましょう。
僕は提案する、廊下は走ってはいけないと。
これは「倒置法」を使った文章ですが、表現的にはちょっとカッコイイものの小論文としては0点の文章です。
普通に「僕は廊下は走ってはいけないと提案する」と書きましょう。
話し言葉・カタカナ語・略語は使わない
文章には「話し言葉」ではなく「書き言葉」を使いましょう。
注意すべき代表的な「話し言葉」をまとめておきます。
| 話し言葉 | 書き言葉 |
| やっぱり | やはり |
| たくさんの | 多くの |
| いつも | 常に |
| どうして | なぜ |
| ~けど | ~が |
| でも、だけど | しかし、だが |
「略語」もしっかりと正式名称で書きましょう。
代表的な略語と正式名称をまとめました。
| 略語 | 正式名称 |
| 携帯 | 携帯電話 |
| 部活 | 部活動 |
| 就活 | 就職活動 |
| スマホ | スマートフォン |
| バイト | アルバイト |
略語で気をつけて欲しいことが、何でもかんでも正式名称にしないということです。
「電車」を「電動機付き客車」としたり、「教科書」を「教科用図書」と表記するのはやりすぎです。
「カタカナ語」は絶対とは言いませんが、できるだけ文中では日本語に置き換えるようにしましょう。
| カタカナ英語 | 日本語表記 |
| ショック | 衝撃、動揺 |
| スムーズ | 円滑 |
| メリット | 利点、長所 |
| デメリット | 欠点、短所 |
小論文って覚えることいっぱいありますね…。
心配しなくても大丈夫!
小論文で覚えることはこれくらいで、基本的なルールさえ理解していればもう書けます!
国語教師が教える小論文の書き方
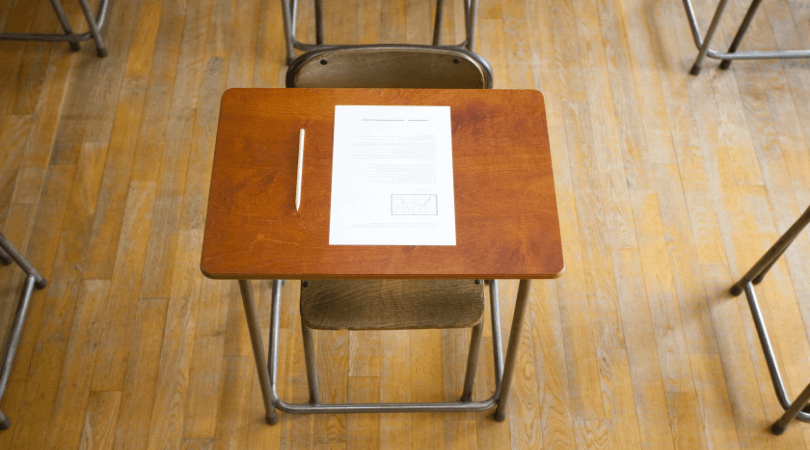
このページを10分程度読み込めば、
小論文が書けるような気がしてきた!
となること間違いなしなので、ぜひ最後までご覧ください。
・小論文の構成
・構成メモの書き方
・序論の書き方
・本論の書き方
・結論の書き方
まずは上記の内容を説明するので、軽く読み進めてください。
後から「例題」と「例文」を使って実際に書いていくので、理解できなくてもOKです。
小論文の構成
「構成」とはザックリ言うと「書く内容」のことです。
初心者にありがちな失敗として「いきなり原稿用紙に書き始める」ことがあげられます。
これは「設計図もなしに家を建て始める」のと同じくらい、危険なやり方です。
小論文を書く前には必ず「構成」を決めなければなりません。
「序論」「本論」「結論」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
これは小論文の代表的な構成の例です。
この構成に従って書けば、的外れなことを書くこともなくなる超基本的な構成の方法です。
それは聞いたことあるけど、何を書けばいいか分からないです…。
僕がおすすめする構成の方法は以下の通りです。
・問題提起(序論)
↓
・原因分析(本論)
↓
・解決策(結論)
基本的に小論文試験というもので求められているのは、「課題を見つけて自分なりの解決策を考える力」です。
上記の構成を使えば、あらゆる出題形式の試験に対応できます。
小論文では「構成」が絶対に必要です!
実際には書き始める前に、余白などに「メモ」として書いていきます。
構成メモの書き方
構成は問題用紙の余白部分に「メモ」という形で書いていくのが一般的です。
書き方に決まりはなく、自分が「これで最後までしっかり書ける!」と思ったら十分です。
この「構成メモ」がないと、指定の文字数を超えたり、逆に少なすぎたり、主張が最初と最後で変わっていたり、何が言いたいのかわからなくなったりしてボロボロの文章になってしまいます。
必ず「最後まで書ける!」と確信を持てるところまで詳しく書きましょう。
構成メモは以下の手順で書いていくと、スムーズにできます。
①課題文(テーマ・資料)の分析
②問題点をあげる
③原因を分析する
④知識・体験を加える
⑤解決策を考える
⑥整理して順番、段落構成を決める
基本的に構成メモは箇条書きをおすすめします。
メモが文章になっていると、文章を原稿用紙に写すという二度手間になってしまいますので、メモには重要な要素だけをシンプルに書いていきましょう。
構成が大事なのは分かりましたが、なかなか書き出せません…。
小論文は書き出しが難しいですよね…。
次は、「誰でも簡単に書きだせる7つの方法」を解説するよ!
序論の書き方(書き出し)
書き出しは意外と難しく意見はまとまっているのになかなか書き始めることができない、という人は多いです。
序論は採点者の印象を決める重要な部分なので、変な書き方をして減点されないように注意しましょう。
困ったら「意見提示をする」という方法が無難で、減点もされにくいです。
意見提示とは簡単に言うと、結論を先に示すことです。
~に対して私は○○と考える
~の問題点は○○と主張する
え、先に結論言っちゃっていいんですか?
大丈夫です!
最終的に結論で同じ内容を述べることになっても、「なぜそのような考えに至ったのか」という部分が大事だからです。
序論の書き方には、以下の7つのパターンを覚えておくと便利です(中級者向け)。
1.意見提示をする
2.賛成、反対を示す
3.一般論から広げる
4.自分の経験から始める
5.具体例を出す
6.課題文を引用する
7.テーマの解説をする
➡【小論文の書き出し】簡単に書ける7つの例文のページで詳しく解説しています。
本論の書き方
小論文の構成の中で大部分を占めるのは「本論」です。
本論には序論で述べたことの展開という重要な役割があり、本論に何を書くかによって説得力が変わります。
基本的に本論は「問題に対する原因分析」を行う段落で、以下のことを中心に書いていきます。
①知識・情報
②体験・経験
③引用・資料
①「知識・情報」は正確なデータを記憶している必要があり、③「引用・資料」はそもそも資料がなければ書くことはできません。
つまり基本的に本論は②「体験・経験」を使って書いていくことになります。
体験や経験は自分だけのものであり、書き方次第で何倍にも価値あるものに変わります。
説得力がある「評価の高い体験談」を書くには3つの要素が重要です。
①自分の体験と照らし合わせる
②具体例をあげる
③課題の問題点を自分なりに考える
上記に加え、今までの自分の活動や人との関わりを整理すると評価の高い体験談を書くことができます。
でも私、そんなすごい体験談なんてないです…。
大丈夫です。そんな人でも評価の高い体験談を書く方法があります。
➡部活・委員をやってない人でも評価の高い体験談を書く方法
さらに、この本論に「反論」を加えるとレベルの高い小論文を書くことができます。
小論文に反論は必須ではないですが重要性は高いです。
そもそも小論文とは「論理で相手を説得する文章」です。
誰かを自分の論理で説得しようとしたとき、相手から反論を受けることはよくあることですよね。
小論文ではそのような「自分の意見への反論」に対して、論理的に対応できると説得力が上がり、評価が高くなります。
結論の書き方
よく「結論にはまとめを書くのが良い」という意見を聞きますがまとめは書かなくてよいです。
採点者もプロですから、800~1200字程度の文章の内容を読んでいるうちに忘れてしまい、最後にまとめが必要になるなんてことはありえません。
それよりも結論に書く必要があることは、問題の「解決策」です。
学校側は「問題解決意識」を持った学生・生徒を欲しています。
解決策は以下の2つの視点から書くと良いです。
・現実的かつ具体的な案
・自分ができること・していること
特に「自分ができること・していること」は欠かさず書きましょう。
そして文章の終わり方は、希望を持ったポジティブな印象で締めましょう。
「希望ある未来を自分で切り開いていく」という書き方にすれば、読後感がすっきりするのでおすすめです。
う~ん、なんとなく書き方は分かった気がするんですけど。
いざ書こうってなると、どうすればいいか分からないんですよね…。
では、実際に例題を解きながら、具体的にどうやって小論文を書いていくかを解説します。
テンプレ例文を使って小論文を書こう!
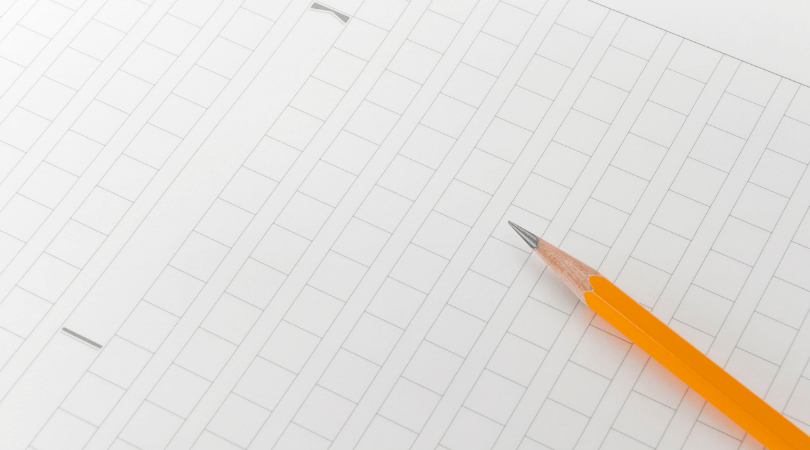
具体的な例題と例文を使って、小論文の書き方を解説していきます。
初心者の人は「テンプレ例文」を参考に、志望校の過去問などを見て「先生に見せられるレベルの小論文」を書いてみましょう。
例題
「SNSの実名制の導入」について、800字程度であなたの意見を述べなさい。
上記の例題で、1から10まで具体的に小論文を書いていきます。
具体的な構成メモの書き方
例題
「SNSの実名制の導入」について、800字程度であなたの意見を述べなさい。
最初にすることは、問われている内容を見て答え方を間違えないようにすることです。
太字で書いてあるところが重要ポイントで、この条件を満たす解答を作ります。
うわ、800字って原稿用紙2枚分じゃん…。
こんなの書けない…。
大丈夫です。構成の段階で書くことを決めれば、800字って意外と余裕です。
序論の構成を作る
~に対して私は○○と考える
~の問題点は○○と主張する
書き出しの方法は「意見提示」がカンタンです。
問題は「SNSの実名制の導入」なので、これに対して自分の意見を提案しましょう。
う~ん、まぁSNSが実名制になっても私は良いと思うかなぁ。
いい点ばっかりじゃないと思うけど…。
序論の構成メモ
・SNSの実名制の導入
→賛成で利点も多いが問題点もある
「賛成」「反対」の立場を最初に示すと、意見が一貫してブレないのでオススメです。
本論の構成を作る
本論は「問題の原因分析」
体験談・反論を使えば説得力アップ
本論が一番ボリュームの多いところなので、しっかりと内容を考えましょう。
まずは「問題の原因分析」です。
「SNSの実名制の導入」が議論される原因って、やっぱり誹謗中傷だよね。
有名人が自殺しちゃうニュースとかよく聞くし。
その調子です。次はそれに「自分の体験談」も加えて説得力を増していきましょう。
私も知らないアカウントから急に悪口言われたことあるし、それでめっちゃ傷ついたのに、匿名だから相手のことは分からなくてモヤモヤしたし…。
SNSが実名制になれば、こんな気持ちにならなくて済むよね!
しっかり「自分の意見」を考えられていますね!
次は「反論」を入れるとさらに説得力がアップします。
SNSの実名制に反対する意見って言えば…、「言いたいことが言えなくなる」かなぁ。
でも「Facebook」とかって世界中の人が使ってるけど実名制だし、それであんまり不便してないんじゃない…?
「反論」に対する「対抗意見」が考えられるとかなり評価の高い小論文になります。
では、以上の考えをメモにまとめてみます。
本論の構成メモ
・「SNSの実名制の導入」が議論される原因
→不特定多数の誹謗中傷
→匿名による特定の難しさ
・自分が賛成する理由
→過去に匿名アカウントに誹謗中傷を受けた
→実名制になれば傷ついて、最悪自殺してしまう人を救える
・「反対派」の意見とそれに対する反論
→実名制になれば「正しい批判」ができなくなる
→実名制で世界的に使われているSNSはある
結論の構成を作る
結論に書くのは「解決策」
・現実的かつ具体的な案
・自分ができること・していること
結論には具体的な解決策を書いていきます。
「SNSの実名制の導入」の背景には、「匿名での誹謗中傷」という問題があると本論で分析しましたね。
匿名での誹謗中傷をなくすには、SNSの実名制の導入以外の方法もあるよね。
例えば、学校教育の道徳の授業で誹謗中傷について取り入れるとか。
具体的な解決策が思いついたようですね。
最後は「自分が取り組んでいること」を入れて文を終えると、読後感が良く追われるので採点者にも好印象です。
私ができることは、匿名での誹謗中傷は行わないことかな。
あと、匿名での誹謗中傷で傷つている友達がいたら、相談に乗ってあげることもできるかも。
これで、構成が完成しましたね。
結論の構成メモ
・匿名での誹謗中傷をなくす解決策
→学校教育で誹謗中傷について取り上げる
・自分が取り組めること
→誹謗中傷を行わない
被害を受けた人の相談に乗る
これで「小論文の設計図」ができたので、実際に文章を書いていきます。
構成メモを元に書いた例文
例題
「SNSの実名制の導入」について、800字程度であなたの意見を述べなさい。
構成メモ
〇序論
・SNSの実名制の導入
→賛成で利点も多いが問題点もある
・「SNSの実名制の導入」が議論される原因
→不特定多数の誹謗中傷
→匿名による特定の難しさ
〇本論
・自分が賛成する理由
→過去に匿名アカウントに誹謗中傷を受けた
→実名制になれば傷ついて、最悪自殺してしまう人を救える
・「反対派」の意見とそれに対する反論
→実名制になれば「正しい批判」ができなくなる
→実名制で世界的に使われているSNSはある
〇結論
・匿名での誹謗中傷をなくす解決策
→学校教育で誹謗中傷について取り上げる
・自分が取り組めること
→誹謗中傷を行わない
被害を受けた人の相談に乗る
この構成メモを元に書いた例文がこちらです。
SNSの実名制の導入について、利点が多いことから私は賛成である。しかし、現実的に全てのSNSで実名制を導入することは難しく問題も多い。なぜSNSの実名制の導入が議論されるのか、という原因から利点について論じていく。
SNSの実名制が議論される原因として、匿名での誹謗中傷の問題があげられる。近年、炎上という言葉を頻繁に耳にする。これは、特定の人物がSNS上で批判や誹謗中傷を数多く受けている状態のことを指す。正しい批判ならともかく、人格を否定するような誹謗中傷は本人の精神を深く傷つけ、最悪の場合自殺に追い込んでしまう。SNS上の誹謗中傷は匿名であることがほとんどなので、被害者は相手を特定することが困難である。私自身もSNSを活用しているが、いわれのない誹謗中傷を匿名アカウントから受けて深く傷ついたことがある。それらは匿名であるがゆえに行われることであり、実名をさらしてまで他人を誹謗中傷する人は少ないだろう。SNSの実名制が導入されれば、誹謗中傷による被害者を少なくすることができる。
しかし、SNSが実名制になれば「言いたいことが言えなくなる」という問題も浮上してくるだろう。匿名だからこそ世の中に発信できることもあり、言論の自由を脅かすのではないかという主張である。ただ、世界的に利用されているFacebookなどの実名制SNSでは自由な議論が展開されているのが事実である。実名で発信することによって自分の発言に責任が生まれ、より慎重にSNSを利用するようになると思われる。よって、SNSを実名制にしても、言論の自由は妨げられないと考える。
SNSの実名制の導入は現実的には難しく、今後も匿名制と実名制の両方のSNSを上手く使分けていく必要がある。また、匿名での誹謗中傷で傷つく人を減らすため、学校教育の道徳の授業等で誹謗中傷を取り扱うことが解決策の一つになると考える。私自身も誹謗中傷行わず、正しい知識や教養を身につけてメディアリテラシーを高めたいと考えている。(799字)
構成が分かりやすいように、序論・本論・結論で間をあけていますが原稿用紙では間をあける必要はありません。
800字って多いと思ってたけど、構成メモを作ったら書けました!
文字数に合わせて構成メモの内容を増やしていけばいいので、構成メモさえあればどんな問題が来ても書けます!
【写して完成】小論文のテンプレ例文
テンプレートにそって間を埋めていけば、800字程度の小論文を完成させられます。
先生に「とりあえずなんか書いてきて」と言われて困っているなら、以下のテンプレを元に書いてみましょう。
序論のテンプレ
(問題のテーマ)について、私は(賛成・反対)の立場をとる。なぜなら、~だからである。ただ、(問題のテーマ)には問題点も多く、慎重に議論すべきであると考える。なぜ(問題のテーマ)についての議論が起こるのかという原因から、(賛成・反対)の理由について論じる。
本論のテンプレ
(問題のテーマ)が議論される原因として、▲▲があげられる。▲▲とは~である。近年、~のような問題が社会の課題となっている。
私自身も(問題のテーマ)について、関心があり□□のような経験をしたことがある。~をすればこのような問題は解消されると考える。
しかし、○○という反対意見もある。確かに○○は~だが、◆◆という考え方もできる。よって、○○という反対意見もあまり問題にならないのではないかと考える。
結論のテンプレ
▲▲という問題の解決策の一つとして私は、●●を提案する。これによって~が改善されると考えられる。また、私自身も~という取り組みを行っており、少しでも問題解決に貢献できるように勉強を続けていくつもりである。
例えば、以下のようなテーマで上記のテンプレ例文に当てはめて書いてみましょう。
例題
「AIの導入による仕事の効率化」について、あなたの意見を述べなさい。(800字)
例題
「企業のSDGsに取り組むこと」について、あなたの意見を述べなさい。(800字)
例題
「食品ロス」の問題を解決するためはどのような方策を講じるべきか。あなたの意見を述べなさい。(800字以内)
小論文の時間配分
小論文は「時間配分」がかなり重要です。
800字/60分のスタンダードな試験形式での時間配分は、以下の通りです。
問題を分析する(5~10分)
↓
構成をつくる(15~20分)
↓
解答用紙に清書する(20~30分)
↓
見直しをする(5~10分)
とにかくまずは問題文を読んで「構成メモ」を作ってください。
解答用紙に書き始めるのは、完全に構成が1から10まで固まってからです。
試験時間別の時間配分の例は以下の通りです。
| 時間 | 分析 | 構成 | 清書 | 見直し |
| 30分 | 5分 | 5~10分 | 10~15分 | 5分 |
| 60分 | 5~10分 | 15~20分 | 20~30分 | 5~10分 |
| 90分 | 5~15分 | 20~30分 | 30~40分 | 5~10分 |
| 120分 | 10~15分 | 25~30分 | 40~60分 | 15~20分 |
あくまで目安なので、自分に合った時間配分を見つけてください。
ただ、何度も言いますが「構成メモ」には必ず十分な時間を取ってください。
小論文の採点基準
最後に採点基準について解説します。
小論文の採点基準に一律のものは存在しません。
しかし、合格する小論文には共通する3つのポイントがあります。
このポイントをおさえておけば、どんな志望校の採点基準でも大きく減点されることはなくなります。
そのポイントとは以下の通りです。
①問題文を正しく読み解いているか
②自分独自の意見か
③正しい文章構成・表現か
上記のポイントをしっかりとおさえた小論文は高い評価を得ることができます。
採点基準を知れば、合格する小論文が書けますね!
具体的な書き方は分かりました!
でも、小論文ってどんな感じで出題されるんですか?
主に5つのパターンで出題されるよ!
自分の志望校が、どのパターンで出題してくるかは必ずチェックしよう!
小論文の出題形式
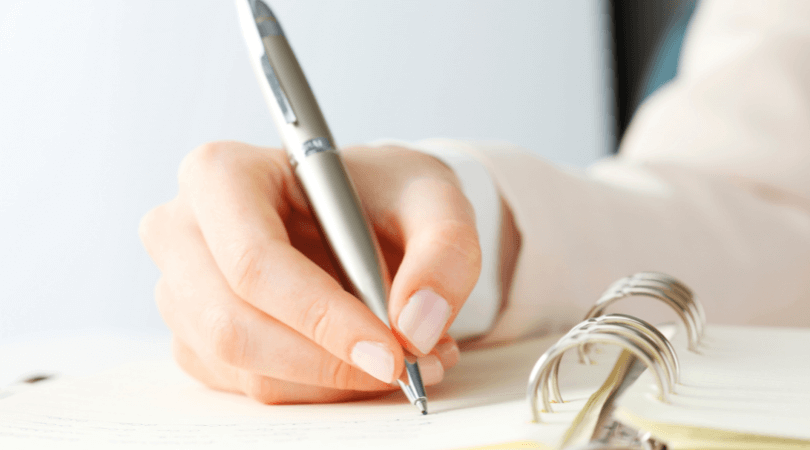
書き方が分かれば、次の対策は「出題形式を知ること」です。
一口に小論文試験と言ってもただ書くだけはでなく、読解力を必要とするものや、資料のデータを正しく比較する力を必要とするものなどさまざまな形式があります。
志望校の過去問をチェックして、どのような出題形式になっているかを見てみましょう。
ここでは主な5つのパターンの出題形式を解説します。
・テーマ型
・課題文読解型
・資料分析型
・要約型
・志望理由型
さらにこれらが複数組み合わさった「複合型」の形式もあるので、すべてに対策が必要となります。
では上から順番に解説します。
テーマ型
例題
「SNSの実名制の導入」について、800字程度であなたの意見を述べなさい。
与えられたテーマに対する自分の意見を論述する形式です。
一番オーソドックスな試験形式で、あらゆる学校・企業が採用している方法です。
対策としては、自分の志望する分野の情報に普段から触れておくことと、それに対して常に自分の意見を考えることです。
課題文読解型
例題
次の文章をよく読み、以下の問いに応えなさい。
①文章を200字以内で要約しなさい。
②筆者の主張に触れながら、あなたの意見を1200字以内で述べなさい。
与えられた課題文を読み、それに対する自分の意見を論述する形式です。
難関校になるほど課題文が長文になる傾向にあり、文章の内容も複雑になります。
制限時間内に課題文を読解し、その内容をふまえて自分の意見を構築して論述していくのでテーマ型以上に対策が大変です。
現代文の勉強等を通して、読解力を鍛えることが対策となります。
資料分析型
資料として図やグラフが与えられ、それを分析した結果を論述する形式です。
理系の学部や、文系では経済学部・福祉・教育系の学部などに多く見られる出題形式です。
資料の全体像を正確にとらえ、数字をしっかりと比較する力が要求されます。
文章読解力とはまた違う読解力が要求されるので、図やグラフに慣れることを中心に勉強しましょう。
要約型
与えられた課題文を読み、それを指定時数で要約する形式です。
課題文読解型とよく複合形式で出題されます。
課題文が長いほど要約が困難になります。
読みながら要点をマーキングしていくことが、時間短縮のコツです。
新聞の200時要約などのワークブックを、1冊仕上げるのが対策としては良いでしょう。
志望理由型
学部・学科への志望理由を論述する形式です。
大学側は特に「なぜうちの大学を選んだのか」が知りたくて、試験を課しているので、志望大学の理念や教育方針、特色などを知っておく必要があります。
自分の意見がブレないように、慎重に構成を決めてから書いてきましょう。
小論文の頻出テーマ

出題形式が分かれば次に気になるのが「具体的にどんな問題が出るのか」だと思います。
主に小論文では「社会問題」がよく取り上げられます。
これは全分野・全学部通して頻出です。
なぜなら学校側は小論文試験を通して、「課題を見つけて自分なりの解決策を考える力」が学生にあるかどうかを見たいからです。
また、テーマが複合されて出題される場合もあるので、自分の進みたい分野の社会問題だけでなく、社会全体の問題に目を向ける必要があります。
では分野別に頻出テーマを一覧したので、目を通してみてください。
・人文・教育
・社会科学
・理系
・医療
・全分野共通
人文・教育の小論文
人文・教育系は身の回りのことがテーマになり、出題されます。
教育系
・教育格差
・オンライン授業
・9月入学
・キャリア教育
・待機児童問題
・保育士(園)の不足
語学系
・留学の必要性、重要性
・異文化交流の重要性
・小学校からの英語教育
・難民、移民の受け入れ問題
・グローバル化で必要なこと
福祉系
・貧困問題
・介護疲れ
・老老介護
・超高齢化社会
・介護士の賃金問題
・障害者への偏見の改善
社会科学の小論文
社会科学系は、法学・政治学・経済学・経営学がベースのテーマが頻出です。
法学系
・成人年齢(選挙権)の引き下げ
・国際社会における法の役割
・ヘイトスピーチ規制法
・生活保護の増加、不正受給
・誹謗中傷問題
経営系
・雇用問題
・同一賃金制
・年功序列賃金制
・コンプライアンス
・働き方改革
・有給、産休、育休
・パワハラ、セクハラ
経済系
・消費税増税
・税制度
・年金問題
・地方創生
・有効求人倍率
・失業率
理系の小論文
理系の小論文は、高校理科の教科書レベルの知識をつけておくのが前提です。
理学系
・金属鉱物資源問題
・ゲノムと遺伝子
・IPS細胞(人工細胞)
・ヒートポンプ
・プレートの活動
工学系
・未来の機械技術について
・施設、建築の技術
・新サービス、新機能
・ウェアラブルデバイス
・自動運転技術
医療の小論文
医療系は小論文試験を課しているところが多く、あらゆる問題に冷静に対応できる能力が評価されます。
医学系
・再生医療
・尊厳死、安楽死
・投薬による延命の意義
・クローン
・臓器移植
・末期医療
・未知のウイルス、感染症
・手術ロボットの導入
看護系
・認知症ケア
・出生数の減少
・リハビリサポート
・チーム医療
・看護師の夜勤
・臨床現場における看護師の役割
全分野共通
全分野共通の頻出テーマとして国際的な時事問題と、自己理解を解説します。
時事問題(2021年)
・新型コロナウイルス
・東京オリンピック
・人種差別
・Eスポーツ
・GAFA
自己理解
・志望理由
・入学後に取り組みたいこと
・中高時代に頑張ったこと
・将来の夢
・尊敬する人物
小論文の効率的な勉強法

小論文は「読解力」「論理的思考力」「文章力」を必要とするので、教科科目とは勉強の仕方が違い、実力も伸びにくです。
なので勉強開始の時期はなるべく早い方が良いです。
志望校を決めた後に小論文試験があるとわかったら、すぐに勉強を開始してください。
僕がおすすめする効率的な勉強法は、以下の通りです。
・現代文の勉強時間を増やす
・過去問に取り組む
・参考書で問題演習
・添削指導を受ける
では上から順番に解説します。
現代文の勉強時間を増やす
現代文の勉強はそのまま小論文の勉強につながります。
入試に小論文がある場合は、まずは現代文の勉強時間を増やしましょう。
・評論文を読んで読解力をつける
↓
・記述問題に取り組んで文章力の基礎を固める
↓
・要約に取り組んで力試し
このように現代文の勉強は、文章を書くことに対する抵抗感を減らすことができます。
過去問に取り組む
評論文である程度論文の構成に慣れ、記述や要約で文章を書くことへの抵抗が無くなったら、志望する大学の過去問に取り組みます。
その場合過去5年分ほどさかのぼって取り組み、出題テーマの分析と出題形式に慣れることを意識しましょう。
過去問に取り組むときに、意識するべきことは以下の通りです。
・頻出テーマの確認
・出題形式の確認
・試験方式の確認(時間、文字数など)
これらをもとに勉強方針を立てていきましょう。
参考書で問題演習
参考書は自分に合ったものを選びましょう。
どんな参考書を何冊買えばいいか分からない!という方は以下を参考にしてください。
難関校に挑む人
・書き方の参考書1冊
・分野別対策の参考書1冊
・時事問題等の教養参考書1冊
難関校以外の人
・書き方の参考書1冊
特に書き方の参考書は「1冊を完璧に仕上げる」という方法がおすすめです。
添削指導を受ける
小論文の自己採点には限界があります。
試験が近づいてきたら、必ず第三者の添削指導を受けましょう。
添削は基本的に学校の国語の先生にしてもらうと間違いないですが、塾に信頼できる先生がいる場合は、そちらでも構いません。
頼れる先生がいません…。
塾にも行ってません…。
「学校の先生にも塾の先生にも頼ることができない!」という人はWEBの添削サービスを使いましょう。
\おすすめの添削サービスはこちら!/
これらのサービスを使えば、小論文の独学は可能です!
小論文のおすすめ参考書

最後におすすめの参考書を紹介します。
小論文の参考書は、書き方の手順書を1冊買って仕上げれば十分です。
逆に書き方の手順書を何冊も買ってしまうと、どの方法で書けばいいか分からなくなってしまうので、おすすめしません。
書き方を習得したらどんどん問題演習に取り組む方が、実力をつけやすいです。
では以下の3つのジャンルに分けて、それぞれ3冊ずつ僕のおすすめを紹介します。
・書き方の参考書3選
・分野別対策の参考書3選
・時事問題等の教養参考書3選
小論文の書き方の参考書3選
小論文は自己流で書いても絶対に合格しないので、ある程度最初は参考書を読んで型を身につける方法がベストです。
落とされない小論文
Amazonランキング1位の定番参考書です。
初心者~難関校志望者まで対応できるので、迷ったらこの参考書で間違いないです。
採点者の心をつかむ合格する小論文
初心者には少し難易度が高いですが、採点者側の心理を学ぶことができるという新しい視点の参考書です。
本編はスラスラ読める講義形式で、分かりやすいたとえ話も多いのが特徴です。
小論文これだけ!超基礎編
入試小論文界の重鎮である樋口裕一先生の著書で、Amazonランキング2位の参考書です。
「小論文これだけ!」シリーズは他にも多く出版されていて、後に紹介する分野別対策の参考書と併用するなら、この「小論文これだけ!超基礎編」を買っておくことをおすすめします。
小論文の分野別対策の参考書3選
「書き方の手順書」を読んで、「どう書くか」を理解したら、自分が受ける志望分野の頻出テーマの対策をすると合格率がアップします!
ここでは小論文試験が課される割合の高い「看護系」「医学系」「教育系」の3つの分野別対策の参考書を紹介します。
書くべきネタが思いつく 看護医療系小論文 頻出テーマ15
本書は看護医療系Amazonランキング1位の参考書で、最重要15テーマを講義形式で学ぶことができます。
特徴は、実際の入試問題に対する2通りの解答例を紹介している点で、状況によって書き方を使い分けすることができます。
世界一わかりやすい 医学部小論文・面接の特別講座
医学部受験は学科試験が重視されがちですが、近年面接や小論文の比率が高まっています。
本書は医学部専門予備校が蓄積したデータとノウハウから、医学部小論文・面接で高得点をとる方法が公開されていて、医学部を受験するなら必須の1冊といえます。
小論文これだけ! 人文・情報・教育編
「情報社会・インターネット」「メディア」「近代・ポストモダン」「学問・大学」といった専門知識の解説から、分野別の書き方を学ぶことができます。
時事問題等の教養参考書3選
これから紹介する参考書は「教養」をテーマにしたものです。
自分の志望分野の時事問題、社会問題、構造や仕組み、社会実験のデータを知っておけば、どんな課題テーマが来ても安心ですよね。
しかもこれらの教養書は、入試以外でも人生において必ず役に立つ知識や考え方を身につけることができるので、難関大志望者以外の人でもおすすめです!
大学入試小論文の完全ネタ本
小論文試験に合格するために欠かせないネタ(頻出テーマ・関連キーワード)が収録された分野別の参考書です。
社会科学編以外にも、「人文・教育系編」「自然科学系編」「医歯薬系/看護・医療系編」などがあり、自分の志望分野をチェックしてみてください。
2023-2024年版 日本と世界の時事キーワード
時事問題は全分野・学部・学科で頻出です。
ジャンルごとに分けられた解説と、オールカラーで見やすく、時事問題の勉強には1番おすすめです。
1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365
国際系のテーマが頻出の学部では、この1冊で世界標準の教養が身につくのでおすすめです。
ニューヨークタイムズベストセラーでアメリカでは470万部刊行されています。
歴史・文学・芸術・科学・音楽・哲学・宗教の7分野から、教養を高める知識を365日分収録するというコンセプトで、読みごたえがあり、すべての高校生に読んで欲しい1冊です。
総合型選抜で受験予定の方へ
あなたが小論文を勉強する理由は、総合型選抜(旧AO入試)や学校推薦型選抜(旧推薦入試)ですか?
だとしたら、専門の塾を検討することをおすすめします。
専門塾が必要な理由
・小論文対策は独学では難しい
・総合型選抜は学校や塾では対策困難
・各大学ごとに必要な対策が違う
現役高校教師の僕がオススメするのは「総合型選抜専門塾AOI」です。

総合型選抜専門塾AOIは、2022年度入試合格率95.2%で日本一の合格実績を誇る総合型選抜(旧AO入試)・学校推薦型選抜(旧推薦入試)専門の個別指導塾です。
難関大学への合格実績も多数あり、オンラインにも対応しているので全国どこからでも志望校の総合型選抜を目指せます。
総合型選抜合格への圧倒的なノウハウを有しているので、推薦で大学に行きたいならココ!という現役教師おすすめの塾です。
\特長・口コミ・料金を詳細に解説!/
\カンタン3分で無料体験予約! /
小論文のお悩みを全て解決します!
以上で本記事は終了です!
最後までご覧いただきありがとうございました!

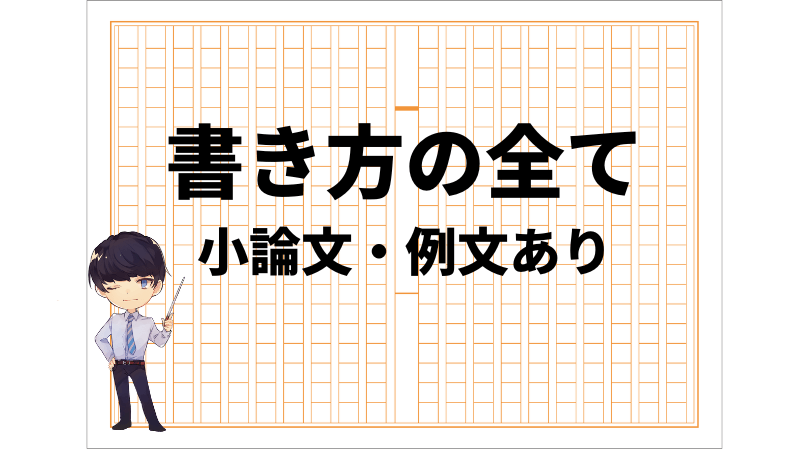

.png)