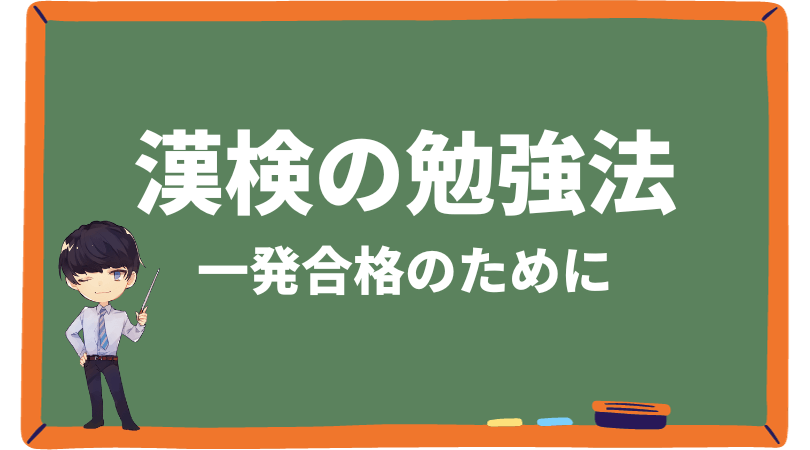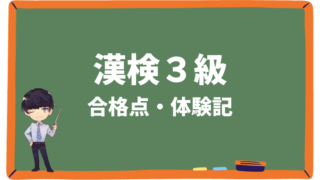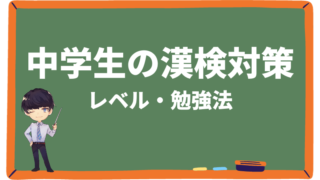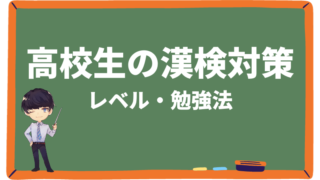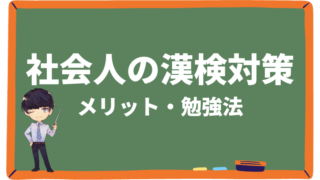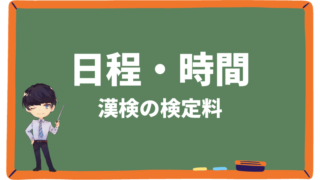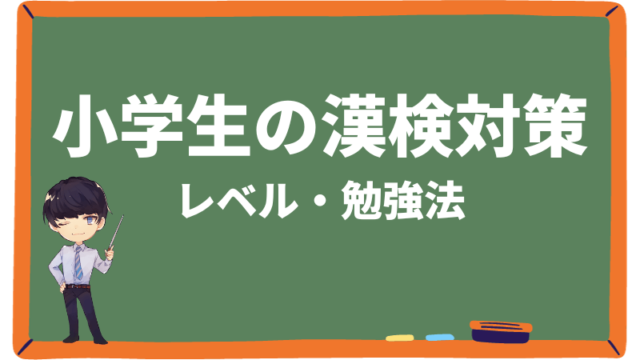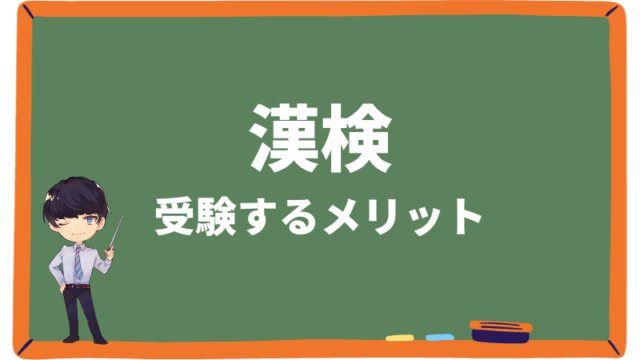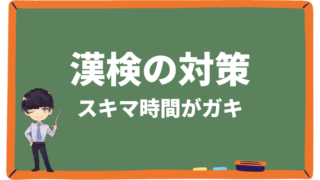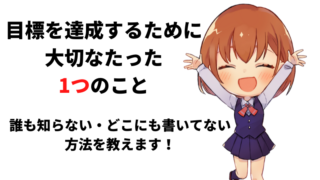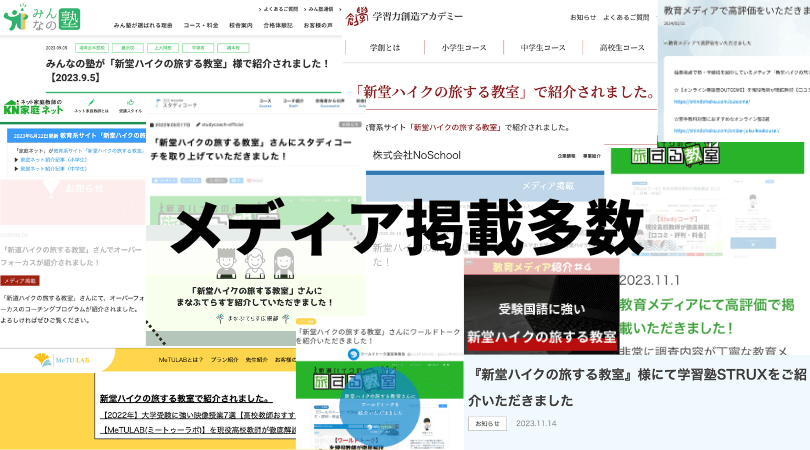こんにちは!
国語教師の新堂ハイクです!
漢検の勉強の仕方が分からない…
「漢字検定の勉強法」について現役国語教師の僕が徹底的に解説します!
漢検は受験料もかかりますし「できれば一回で合格したい!」という人がほとんどですよね。
漢検は2級までの難易度なら、漢字が苦手な人でも一発で合格することは十分可能です。
・現役の高校国語教師
・勤務校で毎年4~2級の合格者多数
・自身も中学生で準2級に一発合格
このページでは、漢検に一発で合格するための効率的な勉強法を紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください!
.jpg)
著者 新堂ハイク 29歳 ・現役高校教師 勤続8年(特進クラス担任) ・難関大受験、小論文指導実績500人以上 ・教育メディア運営6年(月間10万PV) ・執筆300記事以上、掲載企業50社以上 実際の教育現場にいる現役教師にしか分からない、リアルな情報をお届けします!
漢検の勉強法【国語教師が解説】
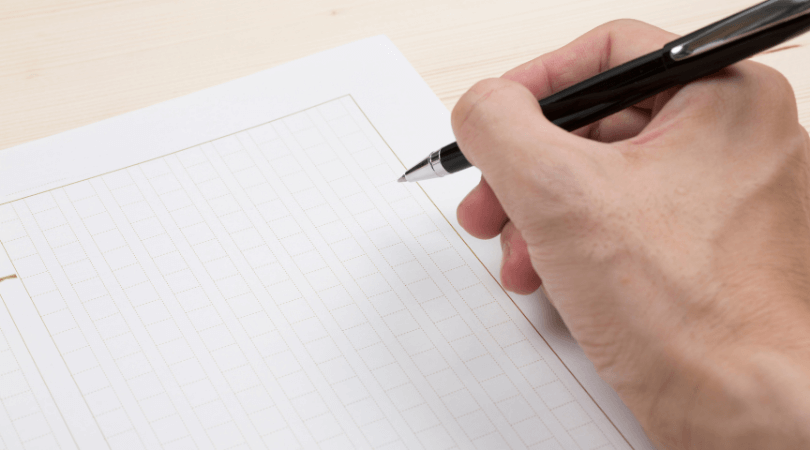
漢字検定の勉強で重要なことを、以下の3点に分けて解説します。
1.勉強計画を立てる
2.漢検の問題集を選ぶ
3.漢検合格の具体的な勉強法【暗記と筆記】
漢検は2級までなら、最大でも2ヶ月ほどの勉強で十分合格できます。
正しい勉強の仕方を覚えて一発合格を目指しましょう。
1.勉強計画を立てる
はじめにすべきことは勉強計画を立てることです。
漢字検定の試験は毎年6月・10月・1~2月の年3回行われ、1か月前まで申し込むことができます。
つまり勉強には最低でも1ヶ月程度の時間が持てるということです。
1ヶ月以上前から勉強を始めたという人も、検定日の1ヶ月前はしっかりと計画を立てて勉強しましょう。
漢検の各級ごとの勉強期間の目安
進学・就職に使える主な級(4級~2級)の勉強期間の目安は以下の通りです。
| 受験級 | 勉強期間 |
| 4級 | 2週間程度 |
| 3級 | 1ヶ月程度 |
| 準2級 | 1ヶ月半程度 |
| 2級 | 2ヶ月程度 |
「漢字が苦手」という人は、上記の期間に「+1~2週間」追加した期間を確保してください。
1日当たりの勉強時間は1~2時間程度で十分です。
・1日のうちにまとまった勉強時間1時間
→問題集やワークを解く勉強中心
・1日の中のスキマ時間を使って1時間
→通勤通学等の時間に暗記中心
このように勉強時間を分けると、効率的に勉強できます。
後にも述べますが、漢検はあくまでも「持っておくと進学・就職に少し有利になる資格」に過ぎないので、学業や仕事が最優先です。
自分の学業・仕事に支障の出ない範囲で勉強計画を立てましょう。
おすすめしない受験時期
4級~準2級は2500円、2級は3500円の受験料がかかります。
できれば一回で合格したいですよね。
しかし、勉強に裏技はありませんので確実な合格を目指すなら、十分な勉強時間の確保が重要です。
なので、中学3年・高校3年・大学4年などの進路に関わる年度に漢検を受験することは避けるべきです。
漢検取得は余裕をもって早めに受験するようにしましょう。
2.漢検の問題集を選ぶ
問題集・参考書選びはかなり重要です。
特に自分に合ったものでなければ、実力を伸ばしにくくなります。
漢検の問題集の選び方としては、以下のものを買うのがおすすめです。
・頻出度順の暗記系の参考書
・書きこみ式のワーク形式の問題集
・漢検公式の過去問
・ノート
暗記系の参考書はスキマ時間に効率よく覚えるために必要です。
また漢検の問題は200点満点中130点が筆記問題なので、書く勉強も欠かせません。
書き込み式のワークを繰り返しノートにして、確実に漢字を書けるように訓練しましょう。
過去問演習も大切で、本番の形式に慣れましょう。
また、過去の問題が何度も出題されていますので、過去問演習が実践演習にもなるので解かない手はないでしょう。
では一つずつ一番のおすすめを紹介します。(商品は3級を基準にしています。)
分野別漢検でる順問題集
迷ったらこれで間違いない!という参考書です。
僕も実際に使いましたし、僕が教えている生徒も多数愛用しています。
この参考書は過去約10年間の漢字検定で出題された漢字を分析し、頻出度順にランク付けされた問題(A、B、Cランク)が分野別で掲載されているもので、本当によく出ます。
特徴としては、付属の赤シートを使って隠しながら書いたり隙間時間に暗記したりすることができます。
使い方は以下の通りです。
①A,B,Cすべてのランクを1巡
②間違った問題にチェックをつける
③A,Bランクの正答率を高める
④Cランクの要点をおさえる
⑤試験直前にチェックした問題の確認
漢検 漢字学習ステップ
漢検を主宰している日本漢字能力検定協会が、公式に出している書き込み式のワークブックです。
各級ごとの新出漢字を一字一字練習することができるので、漢字を覚えるのが苦手な人にもやさしいワークブックです。
使い方は以下の通りです。
①まずは書きこまずにノートにする
②1巡したらワークに直接書き込んで2巡目
③「総まとめ」問題に取り組む
漢検 過去問題集
こちらも日本漢字能力検定協会が出している過去問題集で、過年度実施の検定問題13回分がすべて収録されており、実物大の解答用紙が付属しています。
過去問に取り組むタイミングとしては、受験級を決める前・勉強を開始する前・検定日の1週間前などがおすすめです。
実際の制限時間の60分を守ってチャレンジしてみましょう。
3.漢検合格の具体的な勉強法【暗記と筆記】
問題集を買い、勉強計画を立てたら次は勉強に取り組みましょう。
ここで注意してほしいのが、「漢検」は進学・就職の決め手にはならないということです。
あくまでも資格の一つなので、「漢検」を持っているから進学・就職が決まったということはありません。
決め手になるのは学力やコミュ力などの能力です。
勉強時間はできるだけ最小限に抑えて効率よく合格を目指しましょう。
では効率的な勉強法を解説します!
スキマ時間に暗記を行う
漢字は知っていないと答えられません。
なので「覚える勉強」がメインになります。
特に部首・熟語の構成・四字熟語・対義語・類義語など、日常生活のなかでもほとんど使わないのでなじみがありません。
そういった漢検特有の暗記事項を中心に覚えていきましょう。
スキマ時間は1日の中に数多く存在します。
・朝起きてからの10分程度
・通勤、通学中
・休み時間
・トイレ
・風呂
・歯磨き中
・夜寝る前の10分
こうした時間を利用して暗記を行いましょう。
筆記の勉強はノートを使う
漢字は覚えているつもりでも、正確に書けないことがあります。
あれ、ここって「日」だっけ?「目」だっけ?
ここの横棒って一本だっけ?二本だっけ?
漢字を書く際にこういった経験は誰にでもあるはず。
「覚えていること」と「正確に書けること」は別なのです。
試験本番でこういったことを避けるために、必ずノートなどに書き取りの練習をしましょう。
僕は「漢検ノート」を1冊作ってそこにひたすら苦手な漢字を練習していました。
過去問演習は必ず行う
本番と同様の制限時間(60分)とできれば本番と同じ問題用紙を使って、過去問演習を行ってください。
特にどの問題にどれだけの時間をかけるか(かかるか)をよく考えて、本番の時間配分を決めていきましょう。
書き取り問題は一番配点が高く、問題数も多いのでここに時間をかけたいところです。
読み問題や選択式の問題は早く正確に解答できるように、練習を重ねましょう。
0円でできる勉強法
身の回りにある漢字をよく見て、意味や熟語の構成、部首などを考える方法です。
普通に生活しているだけで、日本人は1日に膨大な量の漢字を読みます。
これらを意識して生活するだけでかなり勉強になります。
問題集を使った勉強などと並行してやってみてください。
漢検の級ごとの勉強法・合格体験記
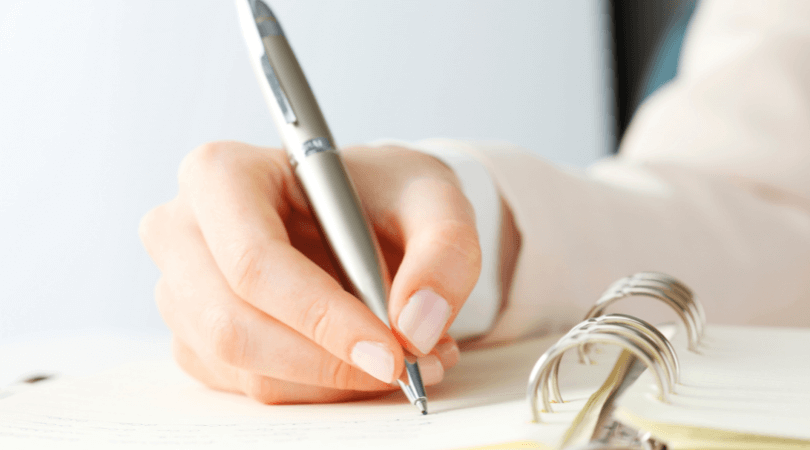
進学・就職で有利になるのは4級~2級です。
ここでは4級・3級・準2級・2級の4つの級ごとの勉強法を解説しているページを紹介しますので、ぜひご覧ください。
漢検4級の勉強法・合格体験記
漢検4級は「漢字が苦手な中学1年生~高校1年生」が初めて検定を受ける級としておすすめのレベルです。
漢検4級のレベル
漢検4級のレベルは中学校在学程度で、漢字が苦手な中学1年生~高校1年生が受けるのに適しているといえます。
200点満点中70%程度(140点程度)が合格基準で、試験時間は60分です。
200点のうち130点分が筆記形式で、70点分がマークシート形式(選択式)になっています。
漢検4級の出題内容
4級の出題内容と配点の目安は以下の通りです。
| 漢字の読み | 30点 |
| 漢字の書き取り | 40点 |
| 四字熟語 | 20点 |
| 対義語・類義語 | 20点 |
| 誤字訂正 | 10点 |
| 送りがな | 10点 |
| 同音・同訓異字 | 30点 |
| 部首・部首名 | 10点 |
| 熟語の構成 | 20点 |
| 漢字識別 | 10点 |
上の表の通りに配点が決まっているわけではありませんが、毎年このような配点で行われています。
漢検4級の勉強法
漢検の勉強でおすすめの暗記方法は以下の4つです。
・書いて覚える
・見て覚える
・声に出して覚える
・意味を覚える
とにかく漢字に慣れることが重要で、漢字の苦手を克服するためには五感を使って覚えていく工夫が大切です。
特に漢検は書き取り問題の配点が高いので、「書いて覚える」ことが大切です。
以下の記事で詳しい「勉強法」や「合格体験談」を解説していますので、ぜひ参考にしてください!
漢検3級の勉強法・合格体験記
3級は「漢字が得意ではじめて漢検を受ける中学生・高校生」におすすめです。
漢検3級のレベル
漢検3級のレベルは中学校卒業程度で、漢字が得意な中学1年生~漢字が苦手な高校1年の人におすすめの難易度です。
出題範囲の漢字数は1607字で、4級の1322字から300字程度多くなります。
200点満点中70%程度(140点程度)が合格基準で、試験時間は60分です。
200点のうち130点分が筆記形式で、70点分がマークシート形式(選択式)になっています。
漢検3級の出題内容
3級の出題内容と配点の目安は以下の通りです。
| 漢字の読み | 30点 |
| 漢字の書き取り | 40点 |
| 四字熟語 | 20点 |
| 対義語・類義語 | 20点 |
| 誤字訂正 | 10点 |
| 送りがな | 10点 |
| 同音・同訓異字 | 30点 |
| 部首・部首名 | 10点 |
| 熟語の構成 | 20点 |
| 漢字識別 | 10点 |
上の表の通りに配点が決まっているわけではありませんが、毎年このような配点で行われています。
出題内容と配点は4級とほとんど同じです。
漢検3級の勉強法
漢字検定の勉強は基本的に「漢字を覚えること」がメインになります。
特に覚える際は「書いて覚える」ようにしましょう。
漢字を”知っている”ことと、”正確に書ける”ことは大きく違います。
特に筆記が130点分と全体の60%を占めているので、読めるだけや知っているだけでは合格点には届きません。
以下の記事で詳しい「勉強法」や「合格体験談」を解説していますので、ぜひ参考にしてください!
準2級の勉強法・合格体験記
漢字が得意な人は初めて受ける級が準2級でも十分合格できます。
漢検準2級のレベル
準2級の難易度は高校在学程度で、高校生なら卒業までには取得しておきたいレベルです。
出題範囲の漢字は1951字で、3級の1607字から300字以上も増えるので難易度が高くなります。
ただ、合格点の基準は70%(140/200程度)と3級と変わらないので、自分の得意な分野で点を取ることができれば、十分合格できます。
試験時間も60分と他の級と変わりません。
漢字が苦手な人でも、1ヶ月程度の勉強時間を確保できれば合格可能です。
漢検準2級の出題内容
| 漢字の読み | 30点 |
| 漢字の書き取り | 50点 |
| 四字熟語 | 30点 |
| 対義語・類義語 | 20点 |
| 誤字訂正 | 10点 |
| 送り仮名 | 10点 |
| 同音・同訓異字 | 20点 |
| 部首・部首名 | 10点 |
| 熟語の構成 | 20点 |
上の表の通りに配点が決まっているわけではありませんが、毎年このような配点で行われています。
3級と違う点は、漢字の書き取り、四字熟語の配点が高くなり、同音・同訓異字の配点が下がっている点です。
また、3級まであった漢字識別が出題されなくなります。
漢検準2級の勉強法
漢字を覚えるのはノートなどに書いて覚える方法が効果的なので、参考書を用意してどんどん書いて覚えましょう。
そしてただ書いて覚えるだけでなく、漢字・熟語の意味を理解しながら覚えるのが大切です。
漢字が分からなくても、前後の文脈から当てはまる意味の漢字を推測できるようになるとかなり漢字に強くなれます!
準2級の範囲は1951字と多いですが、日常生活で使っている言葉ばかりなのでまずは普段から意識して漢字を見るようにしましょう。
以下の記事で詳しい「勉強法」や「合格体験談」を解説していますので、ぜひ参考にしてください!
2級の勉強法・合格体験記
漢検2級は「ここまで取れば常用漢字は完璧にできる」という目安になります。
特に社会人の履歴書では、2級でやっと評価されると覚えておきましょう。
漢検2級のレベル
2級のレベルは高校卒業・大学・一般程度です。
高校卒業レベルと言っても、高校在学中に十分取得できるレベルで、漢字が得意な人は中学在学中に取得できます。
出題範囲の漢字は2136字で準2級の1951字と比べても200字程度増えただけですが、合格基準が厳しくなります。
5級~準2級までは200点満点中70%程度(140点程度)で合格だったのに対し、2級からは80%程度(160点程度)取らなければ合格できません。
漢検2級の出題内容
| 漢字の読み | 30点 |
| 漢字の書き取り | 50点 |
| 四字熟語 | 30点 |
| 対義語・類義語 | 20点 |
| 誤字訂正 | 10点 |
| 送り仮名 | 10点 |
| 同音・同訓異字 | 20点 |
| 部首・部首名 | 10点 |
| 熟語の構成 | 20点 |
上の表の通りに配点が決まっているわけではありませんが、毎年このような配点で行われています。
漢字の読みに関しては30点と比率が高いので、ここは何としても満点を目指しましょう。
漢字の書きは一番配点が高い分野ですが、難易度も高いので8割程度(40点)取れれば合格は固いです。
200点中40点しか落とすことができないので、2級は苦手領域があるとかなり不利です。
漢検2級の勉強法
漢検は2級から難易度がかなり高くなります。
なので、必ず参考書を買って何回も解き直すことがオススメです。
圧倒的おすすめ問題集で、この本1冊を仕上げれば合格できます。
まずはA,B,Cすべてのランクを1巡しましょう。
1巡したらおもにA,Bランクの頻出度の高い問題の正答率を上げるために、1巡目で間違った問題の復習に取りかかります。
最後にCランクも完璧にして、2週間前には最新の過去問で力試しをします。
過去問で合格点に届かなければ、もう一度A,Bランクを1巡して頻出問題の正答率をできる限り上げます。
以下の記事で詳しい「勉強法」や「合格体験談」を解説していますので、ぜひ参考にしてください!
漢検の学年別勉強法・レベル
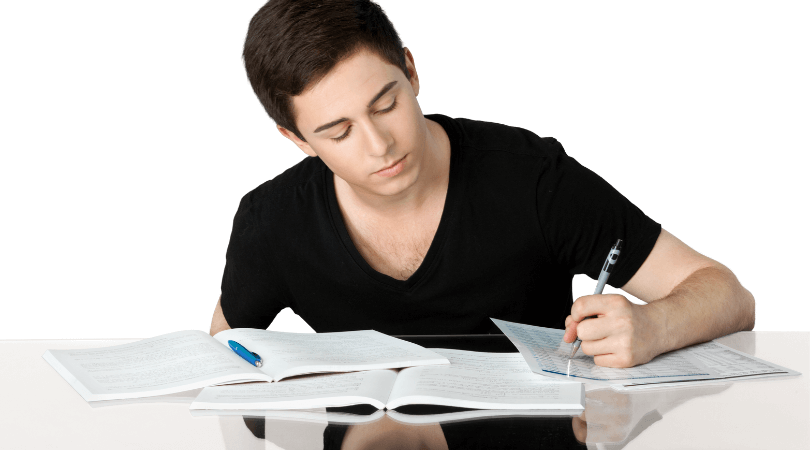
小学生~高校生までの年齢・学年別で解説したページの一覧です。
小学生の漢検勉強法
漢検は小学校レベルの10級から受けられるので、はじめて受ける資格検定として小学生にピッタリです。
小学生が漢検を受けるメリット
・学習習慣が付く
・基礎学力がつく
・自信につながる
漢検の問題は筆記がほとんどなので、書いて覚える学習が必須になります。
毎日15分でも机に向かう習慣をつけることができれば、漢字の学習のみならず他の教科の勉強にも継続的に取り組むことができるようになります。
また、小学生のうちから漢字に強くなると、認識できる情報の量が他の子に比べて格段に増えます。
そして自分の勉強の成果が形となって残るというのは、小学生にとってはかなり嬉しいことで自信にもつながります。
小学生の漢検勉強法
・書いて覚える
・過去問を解く
・スキマ時間に暗記する
漢検の勉強は基本的に「書いて覚える」ことが大前提です。
問題のほとんどが筆記なので、漢字を書けなければ合格することはできません。
「漢検ノート」を1冊作って漢字を書いていくなど、必ずノートなどに書き取りの練習をしましょう。
参考書などは、漢字検定協会が公式で出している書き込み式ワークブックがオススメです。
以下の記事で詳しい「勉強法」や「おすすめ参考書」を解説していますので、ぜひ参考にしてください!
中学生の漢検勉強法
漢字検定は知名度も抜群で取得難易度もやさしいので、最初に受ける検定試験として中学生にオススメです。
中学生が漢検を受けるメリット
・基礎学力の向上
・高校入試の加点
・検定試験に慣れる
特に中学生は受験の際に“内申点”が大きな影響を与えるので、それに加点される漢検は取得しておくとかなり有利にはたらきます。
2019年度の調査では漢検を評価・活用している高校が、4315校にものぼることが明らかになっています。(漢検公式サイトより)つまり、漢検に合格していると、高校入試で直接得点がプラスされたり、内申の評価がアップしたりする可能性が高いということです。
このような内申点のメリットが中学生にとっては大きいですね。
中学生の漢検勉強法
計算問題や応用問題の出ない漢検では「暗記」がとても大切です。
加えて、書き取り問題などが配点の多くを占めるので「漢字が正確に書ける」ように覚えることが大切です。
テキストを見て覚える
ノートに漢字を書き写す
漢字は覚えているつもりでも、正確に書けないこともあります。
あれ、ここって「日」だっけ?「目」だっけ?
ここの横棒って一本だっけ?二本だっけ?
漢字を書く際にこういった経験は誰にでもあるはず。
「覚えていること」と「正確に書けること」は別なのです。
しっかりと書いて覚える勉強をしていきましょう。
以下の記事で詳しい「勉強法」や「おすすめ参考書」を解説していますので、ぜひ参考にしてください!
高校生の漢検勉強法
漢字検定のレベルは準2級が高校在学程度、2級が高校卒業程度です。
高校生は、卒業までに準2級か2級の取得をオススメします。
高校生が漢検を受けるメリット
・大学入試、就活で評価される
・比較的カンタンな資格
・語彙力がついてコミュ力アップ!
大学・短期大学の入試方法が多様化し、取得している資格でも受験者を評価する学校が増えています。
漢検協会公式サイトのデータですが、全国の大学・短期大学の約57%が漢検を評価・活用しているとのことです。
もちろん、漢検を取得してさえいれば大学入試も就活も余裕というわけではありませんが、有利に働くのは間違いないです。
また、高校生は3級以上でないと願書や履歴書に書けないので、必ず3級以上を取得しましょう。
高校生の漢検勉強法
・絶対に書いて覚える
・参考書、過去問に取り組む
・スキマ時間を利用して暗記
高校生のオススメ勉強法は「スキマ時間」を有効活用することです。
パナソニック株式会社が調査した結果では、現代人の隙間時間は1日に平均1時間9分もあるそうです。
・登下校中
・休み時間
・授業が始まって先生が来る間
・朝食、昼食の時間
・トイレ中
・風呂の中
・歯磨き中
このような1日の中にあるスキマ時間をうまく活用して、暗記系の参考書でどんどん暗記しましょう。
以下の記事で詳しい「勉強法」や「おすすめ参考書」を解説していますので、ぜひ参考にしてください!
社会人の漢検勉強法
漢字検定は中高生が受ける検定に思われがちですが、大人が受けてもたくさんメリットがあります。
漢検を主宰している日本漢字能力検定協会も、大人の受験に積極的で年々社会人の受験者も増加しているように思われます。
社会人が漢検を受けるメリット
・社会人の学びなおしに最適
総務省統計局が2016年に実施した「平成28年社会生活基本調査」では、社会人の1日の勉強時間の平均は6分という結果が出ています。
日本の社会人は世界的に見て、かなり勉強時間が少ないと言えます。
そんな中、「漢字検定を受けようかな」と考えてこのページに来たあなたは、意識が高く学び続ける意欲のある数少ない社会人です。
漢検はその取得難易度の低さから、社会人が自主的に始める勉強の足掛かりとして最適です。
漢検は計算やスピーキングなどの実技はなく、完全に暗記のみで取得できるので資格としての難易度はかなり低いです。
いきなり高難度の資格に挑戦して挫折するよりも、比較的カンタンな漢検を通して、社会人でも学んでいく習慣をつけることができるのは大きなメリットといえます。
社会人の漢検勉強法
漢検は暗記メインなので参考書を見て覚えるのが主体の勉強になりますが、漢字の書き取りの配点が高いので書いて覚える練習も必要です。
日中は仕事で忙しい人は、スキマ時間を有効活用して勉強時間を増やしていきましょう。
漢検2級・準2級の取得時間の目安が50~80時間と言われているので、勉強期間は余裕をもって2ヶ月は見ておきましょう。
ちなみに「漢検CBT」という受験方法なら、予約すればいつでも受験できるので忙しい社会人にはそちらがオススメです。
以下の記事で詳しい「勉強法」や「おすすめ参考書」を解説していますので、ぜひ参考にしてください!
おすすめの漢検勉強アプリ

漢検の勉強はスマホアプリでもできます。
特にスキマ時間を有効活用して勉強するために、無料アプリを積極的に使っていきましょう。
漢字検定・漢検漢字トレーニング

対応級:6級~2級
APP内課金:あり(広告費表示)
各級ごとの出題内容に対応した問題を解くことができるアプリです。
また、各級ごとの一覧漢字も載っているので便利です。
iPhoneからダウンロードこちら
androidからダウンロードはこちら
漢検〇級 漢字検定問題集

対応級:4級~2級
APP内課金:なし
級ごとに別のアプリになっており、問題量も豊富です。
書き取りの認識も良く、サクサク進められるのが特徴です。
つくりもシンプルでエンタメ性はほとんどないですが、レビューや評価も高く、信頼性のあるアプリと言えます。
iPhoneからダウンロードこちら
androidからダウンロードはこちら
漢検漢字・漢字検定チャレンジ

対応級:6級~2級
APP内課金:なし
一つのアプリで6級~2級まで対応しています。
書き取り問題の認識も良く、ストレスなく進められます。
シンプルで使いやすいので、スキマ時間にサラッと勉強したい人向けのアプリと言えます。
iPhoneからダウンロードこちら
androidからダウンロードはこちら
おすすめの漢検勉強アプリともっと解説した記事もありますので、ぜひ参考にしてください。
漢字検定の申し込み方法・検定料・受験の流れ

実際に漢検を受験するまでの流れを解説します。
漢検の検定料
おもな受験級の検定料は以下の通りです。
| 検定級 | 検定料 |
|---|---|
| 2級 | 4,500円 |
| 準2級 | 3,500円 |
| 3級 | 3,500円 |
| 4級 | 3,500円 |
2級から値段が上がり、準1級は5,500円、1級は6,000円します。
正直準1級以上は趣味のレベルなので、漢検を取得するなら2級までで十分です。
漢検の申し込み方法
受験申し込みの方法は個人受験の場合は4つあります。
・インターネット
・コンビニ
・取り扱い書店
・取り扱い機関(新聞社など)
漢検の公式ホームページから申し込むことができます。
学生の場合は団体受験で学校が試験会場になることがほとんどなので、学校の漢検案内を見て応募してください。
漢字検定の日程
2024年度の試験日程は以下の通りです。
・2024年6月16日(日)
・2024年10月20日(日)
・2025年2月16日(日)
漢検の申し込みから結果の発表まで
すべての受験級に共通している、検定日の1ヶ月前~検定日の40日後までの流れを解説します。
・検定日1ヶ月前
1ヶ月前までに申し込みを完了しなければ、直近の検定を受けることができませんので忘れず申し込みましょう。
・検定日1週間前
受験表が自宅に届きます
※検定日4日前になっても自宅に届かない場合は、教会へ問い合わせてください。
・検定日当日
各受験会場で検定試験を受けます。
・検定日約5日後
標準解答が漢検ホームページに掲載されるので、自己採点が可能になります。
※2級の合格点は160/200が目安です。
・検定日約30日後
漢検ホームページで合否結果が発表されます。
・検定日約40日後
検定結果資料・標準解答・合格証書・合格証明書が届きます。
※満点合格の場合は「満点合格証明書」という普通の合格証明書よりも豪華な賞状が届きます!
以上が漢検取得の流れです!
漢検に不合格になってしまったら

惜しくも不合格になってしまったら、次の試験日まで勉強して待たなければいけません。
しかし、年3回の受験以外にもいつでも漢検を受けられる方法があります。
それが漢検CBTです。
漢検CBTですぐに受験できる!
「漢検CBT」とはコンピューターを使って漢検を受験することです。
通常の試験と受験方法が違うので、一部出題形式や解答方法が異なる部分がありますが、各級のレベルは紙のテストと同じになるように作られています。
受験料も通常の試験と同じです。
通常の試験と違う点は以下の通りです。
・検定日が限定されない
・検定会場がたくさんある
・10日で結果が分かる
詳しい解説は以下の記事をご覧ください。
惜しくも不合格になってしまったら、取得へのモチベーションが下がらないうちにCBT受験も考えてみてください。
効率的な勉強で一発合格を目指そう!

勉強計画を立て、問題集を選び、暗記と筆記の二つを意識して効率よく漢検合格を目指しましょう!
2024年度の漢検の日程や申込日もお忘れなく!
勉強期間は最低でも1ヶ月程度は確保するようにして、学校や会社と並行して勉強できるような余裕を持つことも大切です。
漢検は知名度抜群で、一度取得すると一生残る資格です。
あなたの合格を応援しています。
以上で本記事は終了です!
最後までご覧いただきありがとうございました!